後醍醐天皇と吉野、歴史の転換点とは?激動の時代を駆け抜けた後醍醐天皇と、その舞台となった吉野の地。
激動の時代を駆け抜けた後醍醐天皇。鎌倉幕府を倒し建武の新政を始めるも、武士や公家の反発で頓挫。吉野に南朝を開き、南北朝時代を招く。天皇親政を夢見た彼の生涯と、南朝の拠点となった吉野の歴史を紐解く。激しい戦いと文化が交錯した、知られざる日本のルーツに迫る。
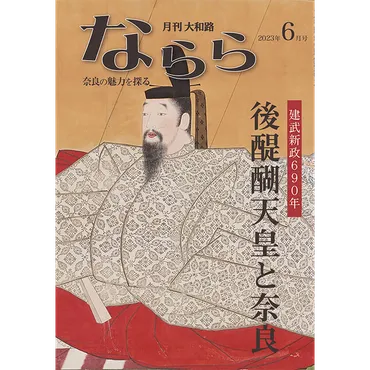
💡 後醍醐天皇の生涯を概観し、鎌倉幕府打倒から建武の新政、そして南北朝時代の幕開けまでを考察します。
💡 建武の新政がなぜ失敗に終わったのか、その原因を探ります。後醍醐天皇の理想と現実のギャップとは?
💡 南朝の拠点となった吉野。その地理的、文化的意義を探り、南北朝時代の吉野の役割を明らかにします。
それでは、まず後醍醐天皇の生涯と、彼が吉野へと向かうことになった背景について見ていきましょう。
後醍醐天皇と吉野
後醍醐天皇はどんな激動の時代に生きていた?
鎌倉幕府崩壊と南北朝時代
後醍醐天皇は、鎌倉幕府を倒し、建武の新政を始めますが、最終的には足利尊氏との対立により吉野へと向かいます。
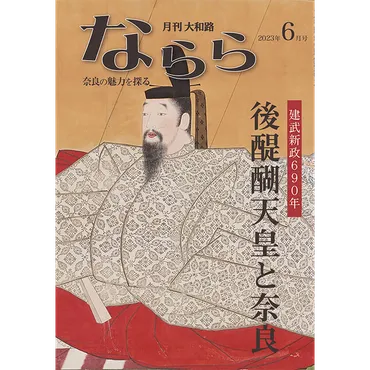
✅ 「ならら」2023年6月号は、建武の新政690年を記念して「後醍醐天皇と奈良」を特集しています。
✅ 鎌倉幕府を倒し建武の新政を行った後醍醐天皇は、悪政とされることもありますが、近年は未来の先例として評価される側面も注目されています。
✅ 本特集では、南朝の舞台を巡りながら、後醍醐天皇の人生と奈良の関係を探ります。
さらに読む ⇒月刊大和路ならら–奈良・大和路の魅力を深発見。出典/画像元: https://narara.co.jp/2023/06/%E3%81%AA%E3%82%89%E3%82%892023%E5%B9%B46%E6%9C%88%E5%8F%B7%EF%BC%9A%E5%BE%8C%E9%86%8D%E9%86%90%E5%A4%A9%E7%9A%87%E3%81%A8%E5%A5%88%E8%89%AF/建武の新政、そして南朝の舞台となる吉野。
後醍醐天皇の人生を読み解くことは、日本史の理解を深める第一歩です。
後醍醐天皇は、鎌倉時代末期の1318年に即位しました。
彼の治世は、鎌倉幕府の崩壊、建武の新政、南北朝時代の幕開けなど、激動の時代となりました。
後醍醐天皇は、鎌倉幕府に対する反乱を主導し、1333年の元弘の乱で鎌倉幕府を滅ぼしました。
その後、建武の新政を開始し、天皇中心の政治体制を確立しようとしましたが、足利尊氏の台頭により失敗し、1336年に京都を追われ、吉野に南朝の皇居を構えました。
吉野は、後醍醐天皇にとって、政治的な避難所だけでなく、文化的な拠点でもありました。
吉野行宮は、約60年間にわたって、南朝の政治の中心地として機能し、南朝の文化や芸術が花開いた場所となりました。
後醍醐天皇と吉野の関係は興味深いですね。建武の新政の詳細や、吉野が選ばれた理由をもっと知りたいです。
建武の新政の崩壊
後醍醐天皇の理想はなぜ失敗に終わった?
武士・公家・民衆の不満が爆発
建武の新政は、天皇親政を目指すも、武士や公家の反発、政策の失敗によりわずか3年で崩壊してしまいました。
公開日:2023/08/24

✅ 建武の新政は、後醍醐天皇が天皇政治の理想を掲げ、醍醐天皇・村上天皇の治世を模範とした改革を志した政治体制でしたが、わずか3年で崩壊しました。
✅ 崩壊の主な理由は、天皇権力の強化が急激すぎて無理が生じたこと、新政府に参加した人々の立場がバラバラで協調性に欠けたこと、そして武家の力が高まる時代に天皇親政という時流に逆行する政策をとったことです。
✅ 具体的には、土地の所有権を天皇の綸旨によってのみ認めるという政策は混乱を招き、新政府は人々の信頼を失いました。また、討幕に貢献した公家や武家の利害が対立し、新政府内部の対立は深まりました。さらに、武家社会においては、幕府の存在を否定したことは、武士たちの力を無視した政策であり、新政の基盤を揺るがすものでした。
さらに読む ⇒世界の歴史まっぷ世界史用語を国・時代名・年代・カテゴリから検索出典/画像元: https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E5%BB%BA%E6%AD%A6%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%94%BF/建武の新政の崩壊は、後醍醐天皇の理想と現実との乖離、そして当時の社会情勢を読み解く上で重要な出来事ですね。
後醍醐天皇は、鎌倉幕府の滅亡後、自身を神に擬して政治を行いました。
彼は、鎌倉幕府の滅亡に貢献した武士や公家に対しては、功績に見合った恩賞を与えようとしませんでした。
また、庶民の生活を改善するための政策もほとんどありませんでした。
特に、後醍醐天皇は、自身の理想を実現するために、武家の権力を抑えようとしたため、武士たちの不満が募りました。
特に、鎌倉幕府を滅亡させた足利尊氏は、後醍醐天皇の政策に反発し、やがて反乱を起こします。
また、後醍醐天皇は、公家たちの権力も制限しようとしたため、公家たちの不満も高まりました。
さらに、庶民たちも、後醍醐天皇の政策によって生活が苦しくなり、不満を抱くようになりました。
このような不満が積み重なった結果、建武の新政は、わずか3年で崩壊し、南北朝の動乱へと突入しました。
その後、足利尊氏が室町幕府を開き、日本の政治は再び武家政権の時代に入ります。
建武の新政の失敗原因は、色々な要素が絡んでいたんですね。後醍醐天皇の理想が高すぎたのでしょうか?
次のページを読む ⇒
鎌倉幕府を倒した、後醍醐天皇。建武の新政、そして南朝へ。激動の時代、吉野を舞台に繰り広げられた南北朝の対立と、天皇の苦難の物語。

