「もののあはれ」とは?:本居宣長と『源氏物語』が教える日本人の美意識とは?本居宣長が説く「もののあはれ」の世界:感情を肯定し、文学作品を通して心を理解する
日本が育んだ美意識「もののあはれ」。感情を素直に受け止め、自然や人間関係を通して心の揺れを感じる感性です。現代の「エモい」にも通じる、切なさや美しさを内包する感受性。本居宣長の思想から現代まで、日本人の心を捉え続ける魅力に迫ります。

💡 「もののあはれ」とは、日本の美意識を表す言葉で、感情の揺れ動きや心の動きを表現します。
💡 本居宣長は「もののあはれ」を重視し、『源氏物語』などの古典文学を通してその重要性を説きました。
💡 「もののあはれ」は、現代の「エモい」という言葉にも通じる感情で、普遍的なものとして存在します。
それでは、本居宣長の「もののあはれ」論について、詳しく見ていきましょう。
「もののあはれ」とは何か?:心の揺らぎを表現する日本独自の美意識
「もののあはれ」って何?日本の美意識をズバリ!
心の揺れを素直に感じ取る感性です。
本居宣長が提唱した「もののあはれ」について、その本質を解説します。

✅ 「もののあはれ」は、心を動かす対象に対して心が揺さぶられる状態を指し、感動、愛情、悲しみなど幅広い心の動きを表す言葉である。
✅ 本居宣長の「もののあはれ」論は、『源氏物語』を理解する上で重要であり、現代の「エモい」という言葉にも似た意味合いを持つ。
✅ 「もののあはれ」は、名詞であり、感情を表す際に使われる一方、「あはれ」や「エモい」とは品詞や使われる意味合いに若干の違いがある。
さらに読む ⇒源氏びより〜源氏物語をどこよりも詳しくやさしく解説〜出典/画像元: https://ryoutei-senryu.jp/monono-aware/「なるほど、感情の揺らぎを表現する言葉なのですね。
確かに、現代の言葉で表現するのは難しい感情かもしれません。
「もののあはれ」は、本居宣長が提唱した日本独自の美意識を表す言葉で、物事に対する心の動きを素直に感じ取る感性を指します。
古代においては、広い意味での「心の動き」を意味し、「もの」は抽象的な対象を、「あはれ」は感動、憐憫、愛情、悲しみなど多様な感情を表します。
現代語の「エモい」に近い表現であり、特定の感情ではなく、心の揺れを包括的に表現します。
具体的には、自然の美しさへの感動、親子の愛情、男女間の慕情、世の無常感など、様々な感情が「もののあはれ」に含まれます。
本居宣長が提唱した「もののあはれ」についての解説、大変興味深かったです!
本居宣長の「もののあはれ」論:感情を肯定し、人間らしさを重んじる思想
本居宣長の「もののあはれ」論、結局何が大事?
感情を肯定し、自然に生きる!
本居宣長の「もののあはれ」論が、人間の感情をどのように捉えているのかを解説します。
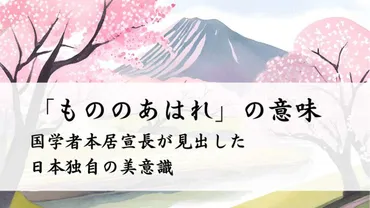
✅ 「もののあはれ」は、本居宣長が提唱した日本独自の美意識で、自然の美しさや人間の感情の儚さに対するしみじみとした感動を意味する。
✅ 本居宣長は、感情を素直に感じ取ることが重要だと考え、「源氏物語」などの古典文学に見られる人間の繊細な感情表現に「もののあはれ」を見出した。
✅ 「もののあはれ」の美意識は、現代の日本人の自然観や文学、芸術、さらには日常生活にも影響を与え続けており、花見や紅葉狩り、映画や文学作品への共感などに繋がっている。
さらに読む ⇒日本神話と歴史出典/画像元: https://rekishinoeki.org/mononoaware/感情を大切にするという考え方は、現代にも通じるものがありますね。
人の心を理解することの重要性を改めて感じました。
本居宣長の「もののあはれ」論は、単なる感情論ではなく、人としての在り方や生き方を重視する思想でした。
彼は、儒教的な道徳観や仏教的な悟りの境地を排し、人間の感情を自然な形で受け入れることに価値を見出しました。
宣長にとって「もののあはれ」は、現実世界を肯定的に捉え、人間的な喜びや悲しみを大切にする生き方の指針でした。
その思想は、感情を抑圧するのではなく、むしろ感情を肯定し、それに寄り添うことを推奨するものでした。
感情を肯定する考え方は、現代にも通じるものがありますね。とても勉強になります!
次のページを読む ⇒
本居宣長の「もののあはれ」論。源氏物語を感情表現の宝庫と捉え、日本人の感性を読み解く。時代を超えた「エモい」感情、その本質に迫る。

