日米開戦への道:近衞文麿は何をしていたのか?(日米関係、近衞文麿、開戦)日米関係悪化と近衞文麿内閣の苦悩:外交、三国同盟、戦争への道
1940年、日本は対米英戦争への道を突き進んだ。近衛文麿内閣による仏領インドシナ進駐と日独伊三国同盟締結は、アメリカとの対立を決定的にした。資源確保のため東南アジアへの進出を目指すが、それは米英との衝突を不可避にする。近衛の平和への願いも虚しく、日米関係は悪化の一途を辿り、太平洋戦争へと突入していく。近衛文麿の苦悩と、その後の近衛家の運命を描く。

💡 近衞文麿は、日米関係悪化の中で、中国との戦争終結と日米関係の改善策を模索した。
💡 三国同盟の締結は、アメリカとの関係を決定的に悪化させ、開戦へと繋がる要因となった。
💡 ABCD包囲網による経済制裁は、日本の資源確保を困難にし、開戦への道を進ませた。
それでは、近衞文麿の外交手腕と、日米関係悪化の中で彼がどのような選択をしたのか、見ていきましょう。
開戦への序曲:日米関係の悪化と近衛文麿の苦悩
なぜ日本は対米開戦へ?近衛内閣の決定とは?
仏領進駐と三国同盟、米への対立激化。
1930年代、日本は軍部の台頭、政治的混乱に見舞われました。
その中で、駐日米国大使グルーは、日米間の関係維持に尽力しました。
しかし、世界情勢の変化は、両国の関係を悪化させていくことになります。
公開日:2022/12/24

✅ 1930年代の日本は、政治的混乱、軍部の台頭、暗殺やクーデターの頻発など、不安定な状況にあった。グルー駐日米国大使は、この時期に日本で外交活動を行い、17人の外務大臣と12人の首相と対峙した。
✅ 日本は近代化と伝統が混在し、アメリカ文化も浸透する一方で、国粋主義が台頭し、日本と西洋の関係を弱体化させようとする動きもあった。二・二六事件など、軍部による政治的な動きが活発化した。
✅ グルー大使は、日米間の貿易や文化交流を維持しながら、日本の政治的変化を見守り、外交の手段としてゴルフなどを通じて関係を深めた。しかし、世界情勢の悪化に伴い、両国の関係は次第に悪化していくこととなる。
さらに読む ⇒The Chicago Shimpo出典/画像元: https://www.chicagoshimpo.com/news-jp/history-talks-american-ambassador-in-tokyo-and-the-countdown-to-pearl-harbor-xjdeg日本とアメリカの関係が、徐々に悪化していく様子が描かれています。
グルー大使の苦労が伝わってきますね。
時代背景を理解することが重要だと感じました。
1940年9月、日本は対米英戦争へと向かう道を歩み始めた。
この動きを決定づけたのは、近衛文麿内閣による仏領インドシナへの武力進駐と日独伊三国同盟の締結である。
これは、アメリカを゛準敵国゛と見なすものであり、駐日アメリカ大使ジョセフ・グルーは日本の変貌に深い懸念を示した。
日米間では、満洲事変以降、アジアの覇権を巡る対立が激化しており、アメリカは日本の中国進出を認めず、1920年代の旧秩序への回帰を求めていた。
同時に、日本国内では、アメリカの経済制裁への不信と反発が強まり、石油などの資源の確保が国家存続の鍵とみなされるようになった。
この状況下、近衛文麿は、ラジオを通じて国民へ平和を訴え続けた。
しかし、そのメッセージが当時のメディア環境下で正確に伝わったかは疑問が残る。
近衛は中国との対立激化を避け、東洋の平和を願っていたものの、その意図は必ずしも国民に理解されなかった。
当時の日本の不安定な状況がよく分かりますね。グルー大使のような立場の人は、本当に大変だったでしょう。外交って難しいですね。
対中政策の転換点:「近衛声明」と日中戦争の拡大
近衛声明、日中戦争をどう変えた?日本の転換点とは?
長期化を決定し、日米関係悪化を招いた。
近衞文麿内閣は、日中戦争の長期化と国際情勢の悪化の中で、対中政策を転換します。
その象徴となるのが「近衞声明」です。
この声明が、日米関係にどのような影響を与えたのか見ていきましょう。
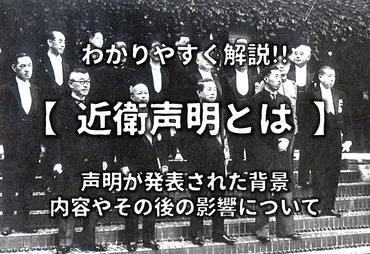
✅ 近衛声明は、1938年に発表されたもので、日中戦争における日本の対中政策を表明し、特に「国民政府を対手とせず」という内容は、アメリカとの開戦を決定づける転換点となった。
✅ 声明発表の背景には、日中戦争の長期化、中国国民党と中国共産党による国共合作、そしてドイツ大使による和平工作(トラウトマン工作)の失敗があった。
✅ 近衛声明は3回にわたって発表され、中華民国との対話拒否、大東亜秩序建設を目的とすることを表明し、その強硬な姿勢がアメリカの対日政策を厳しくした。
さらに読む ⇒日本史事典.com|受験生のための日本史ポータルサイト出典/画像元: https://nihonsi-jiten.com/konoe-seimei/近衞声明が、日本の対外政策を大きく転換させたことが分かります。
アメリカとの関係悪化を招いた原因の一つとも言えるでしょう。
歴史の大きな流れを感じます。
近衛文麿内閣は、1938年に対中国政策に関する声明を発表した。
この「近衛声明」は、盧溝橋事件をきっかけに勃発した日中戦争の長期化と、中国国民党との和平交渉の失敗を背景に発表されたものであり、その中でも「帝国政府は爾後国民政府を対手とせず」という強硬な姿勢は、日中戦争の早期解決を放棄し、より長期的かつ大規模な戦争へと日本を導く重要な転換点となった。
この声明は、アメリカの対日政策を厳しくし、日米関係を悪化させる要因ともなった。
日中戦争勃発の責任を巡り、近衛文麿首相、広田弘毅外相、土肥原賢二奉天特務機関長、杉山元陸相、武藤章参謀本部作戦課長など、多くの人物の役割と影響が詳細に分析されている。
盧溝橋事件は偶発的であったものの、派兵声明が事態をエスカレートさせ、近衛の指導力不足や陸軍内の対立、南京事件における軍紀の低下などが複雑に絡み合い、全面戦争へと繋がった。
近衞声明が、日米関係を悪化させたという点が印象的でした。あの声明がなければ、未来は変わっていたのでしょうか?歴史って本当に面白いですね!
次のページを読む ⇒
日独伊三国同盟が日本の孤立を深め、開戦へ。近衞文麿の苦悩と終戦。名門・近衞家が背負う十字架と、次期当主が語る歴史と責任。

