氷と日本の歴史!平安貴族から現代のかき氷文化まで、日本の氷の歴史を紐解く?かき氷、氷室、製氷技術…日本の氷文化の歴史
平安貴族を魅了した夏の贅沢、氷。貴重な氷を求めた人々の歴史を紐解きます。清少納言が愛した削り氷から、明治維新後の氷ブームまで。かき氷の起源と、人々の知恵と工夫が生み出した多様な文化を解説。今も続く「かき氷の日」や地域振興の動きまで、かき氷の魅力を存分に味わえる情報が満載!
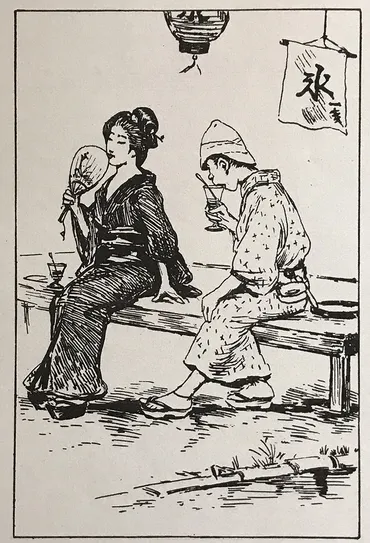
💡 平安時代の貴族が夏の暑さをしのぐために利用した氷室や、削り氷の贅沢さをご紹介します。
💡 氷室の場所や氷室神社の歴史、氷に関わる場所や神社の役割を解説します。
💡 江戸時代から明治時代にかけての氷の普及、かき氷の誕生秘話、その後の発展について語ります。
それでは、日本の氷の歴史を辿る旅に出発しましょう。
各章では、氷にまつわる興味深いエピソードをご紹介します。
平安貴族と氷の文化
平安貴族が夏に楽しんだ贅沢品、それは何?
氷室で作られた削り氷。
最初にご紹介するのは、平安貴族と氷の文化です。
かき氷の日の由来から、当時の氷の利用方法、そして貴族たちの贅沢な食生活に迫ります。
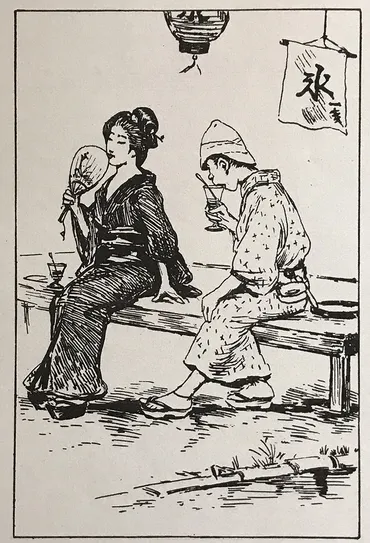
✅ 7月25日の「かき氷の日」の由来は、語呂合わせと日本最高気温の記録に因んでいる。
✅ かき氷は、平安時代には貴族の贅沢品であり、江戸時代末期に氷の大量輸送が可能になり、明治時代に庶民が口にできるようになり、「氷水屋」が日本初のかき氷屋としてオープンした。
✅ 明治時代には、輸入氷に対抗し、中川嘉兵衛が北海道で製氷事業を成功させ、「箱館氷」を販売し、宮内庁御用達にもなった。また、日本初のアイスクリームもかき氷屋で販売された。
さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/rock/gourmet-rock/17343/平安時代のかき氷は、まさに特別な日のご馳走だったのですね。
清少納言が『枕草子』で上品なものとして表現しているのも印象的です。
平安時代の夏、貴族たちは暑さをしのぐために「氷室」を利用していました。
これは、冬に作られた氷を山中の貯蔵庫に保管し、夏に利用するというもので、大変貴重なものでした。
清少納言は『枕草子』の中で、削り氷を「あてなるもの(上品なもの)」として挙げ、甘味料と共に天皇や一部の貴族しか味わえない贅沢品として紹介しています。
大変興味深いですね! 貴族たちが夏の暑さをどのようにしのいでいたのか、当時の生活が目に浮かぶようです。
氷室の場所と氷室神社の歴史
京都の氷室で有名な場所は?どんな祭があるの?
栗栖野氷室跡と氷室神社。献氷祭や氷室の節会。
続いて、氷室の場所と氷室神社の歴史について見ていきましょう。
貴重な氷を貯蔵した場所や、氷を司る神社について解説します。

✅ 京都市西賀茂氷室町は、険しい峠を越えた山奥に位置し、かつて氷を貯蔵する「氷室」があった集落。過疎化が進み、2020年には住民が15名まで減少している。
✅ 氷室は、仁徳天皇に献上された記録があるほど歴史が古く、冷気を蓄えやすい地形を利用して作られた。氷室神社には氷を作った神が祀られており、拝殿はかつての御殿を移築したものである。
✅ 氷室の跡地は、氷池で作られた氷を保管した場所で、現在も丸い窪みが残っている。昔は、氷を口にすると夏を健康に過ごせると言われたが、庶民には手の届かないものであった。
さらに読む ⇒京都旅屋出典/画像元: https://www.kyoto-tabiya.com/2022/08/25/100529/氷室町のような場所で氷が作られていたとは驚きです。
氷室神社のように、氷を司る神社があるのも興味深いですね。
氷室は、京都市北区西賀茂氷室町など、各地に作られました。
『延喜式』には氷室の場所が記されており、現在も栗栖野氷室跡にはその面影が残っています。
京見峠を越え、氷室分かれを経由して栗栖野氷室跡へ至る道のりは、当時の人々の苦労を想像させます。
氷室神社は、元明天皇の勅命により創建され、氷の神を祀り、豊作祈願の祭事が行われていました。
拝殿は、後水尾天皇の内裏小御所の庭にあった釣殿の遺構を活用し、徳川和子が寄進したと伝えられています。
毎年5月1日には、製氷・販売業者が参加し、その年の業績成就を祈願する「献氷祭」が開催されます。
また、宮中では「氷の朔日」に氷を食べる「氷室の節会」が開かれていました。
氷室の場所が具体的に分かると、当時の人々の苦労が想像できますね。祭りの話も楽しみです。
次のページを読む ⇒
平安貴族から現代まで、かき氷は日本の食文化を彩ってきた!歴史を紐解き、氷ブーム、かき氷の日の秘密、そして地域振興まで。冷たいスイーツの奥深い世界へ。

