家督相続とは?制度の始まりから現代の相続事情まで徹底解説!明治維新から現代へ、変化し続ける日本の相続制度
明治時代の日本を変えた「家督相続」制度。長男が家と財産を継承し、戸主が家族を統括する社会構造を紐解きます。武士社会での隠居制度、そして現代の相続制度との比較を通して、家族観と相続の変遷を解説。不平等を生んだ側面と、現代の相続制度との違いを分かりやすく解説します。
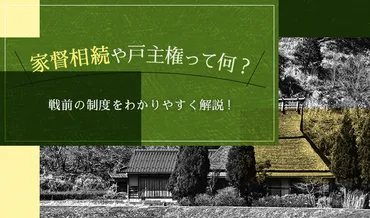
💡 家督相続は、明治時代に法制化され、戸主が家族と財産を統括する制度でした。
💡 江戸時代の長男相続の慣習を基盤とし、戸主権という強い権限が特徴です。
💡 戦後の民法改正により廃止され、現代の相続制度へと移行しました。
さて、今回は日本の歴史の中で大きな役割を果たした「家督相続」について、その制度の始まりから廃止に至るまで、詳しく見ていきましょう。
明治維新と家督相続の始まり
明治時代の家族制度を変えた「家督相続」とは?
長男が財産と地位を相続する制度。
家督相続は、明治維新後の日本で導入された家族制度の根幹を成すものでした。
戸主が家族を統括し、財産を相続する制度として法的に定められました。
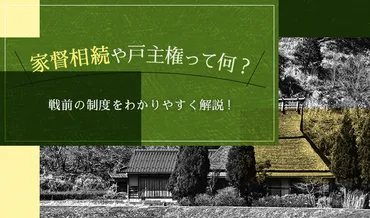
✅ 記事は、戦前の日本で存在した家督相続制度について解説しています。家督とは家産や家業を意味し、戸主が家族を統括する権利を持っていました。
✅ 戸主は家族に対する権利(戸主権)を持ち、家族の変化への同意、居所の指定、家族からの排除といった権限を行使できました。
✅ 家督相続制度は、明治維新で法律に取り入れられましたが、戦後に廃止されました。本記事では、家督相続の背景や、現代への影響についても触れています。
さらに読む ⇒【公式】家系図作るなら家樹-Kaju-|東京の家系図作成専門会社出典/画像元: https://ka-ju.co.jp/column/Inheritance家督相続制度は、日本の近代化を支えた一方、家族のあり方にも大きな影響を与えたことが興味深いですね。
戸主権の強さが印象的です。
明治時代、日本は近代化の波に乗り、家族制度も大きな変革を迎えました。
その中心にあったのが「家督相続」制度です。
これは、江戸時代からの長男相続の慣習を基盤とし、法律によって定められたものでした。
家督とは、元々は家長権を意味していましたが、徐々に家の財産や事業全体を指すようになり、明治維新以降は法律上の権利「戸主権」として確立されました。
戸主は戸籍の筆頭者であり、家族を統括し、家族の変化(婚姻や養子縁組)への同意権、居所の指定権、家族からの排除権といった強い権限を持っていました。
家督相続は、この戸主が死亡または隠居した際に、長男が家の財産と地位を全て相続する制度として、日本の家族制度の根幹を成していました。
なるほど、明治維新が家督相続制度の法的基盤を作ったんですね。戸主権の内容が、現代の相続制度とは全く違うのも興味深いです。
武士の隠居と家督相続
江戸時代の武士、隠居って何歳からできたの?
50歳過ぎから検討、老練を活かす制度。
江戸時代には、身分制度に基づいた相続方法が存在しました。
武士の隠居と家督相続の関係性、隠居相続の手続きについて見ていきましょう。

✅ 家督相続は、戦前の戸籍制度で用いられていた単独相続の制度で、戸主の地位などを次の戸主が引き継いだ。
✅ 江戸時代には、武士の身分によって相続方法が異なり、家督相続は身分の高い武士の間で行われた。
✅ 隠居相続は、家督相続の一種で、隠居する側の年齢制限はなかったが、相続人は原則17歳以上で、老中などの承認を得る必要があった。
さらに読む ⇒東京の家系図屋さん|トップページ出典/画像元: http://edo-kakeizu.com/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%80%80%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%80%80%E5%AE%B6%E7%9D%A3%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%A8%E9%9A%A0%E5%B1%85.html武士の隠居制度は、家督相続と密接に結びついていたんですね。
隠居の手続きや、隠居後の役割など、興味深い点がたくさんありますね。
江戸時代、武士社会では、50歳を過ぎたあたりから隠居が検討されるのが一般的でした。
これは、家督を次の世代に譲り、自身の経験や知恵を活かしながら後進を育てるための制度でした。
隠居には厳格な手続きがあり、上司への願い出と許可、家督相続願の提出、そして老中からの申し渡しという流れで進められました。
家督相続は武士にとって重要なイベントであり、隠居は家格や俸禄の継承、そして次期当主の育成という重要な意味を持っていました。
相続には、生存中の「隠居相続」と死亡後の「死後相続」があり、いずれも幕府への願い出が必要でした。
家督は将軍から与えられるという形式であり、相続は嫡子に限られ、子宝に恵まれない場合は養子を迎える必要がありました。
養子には様々な種類があり、幕府は初期には末期養子を認めていませんでしたが、慶安事件などの社会不安を背景に一定の条件のもとで認めるようになりました。
隠居の理由は、病気や老衰など様々で、70歳を過ぎると理由がなくても許されました。
また、ちょんまげを結えなくなった場合も隠居や出家を選択せざるを得ない状況でした。
隠居の手続きが厳格だったり、隠居理由に年齢制限があったり、まるで現代の定年退職みたいですね!
次のページを読む ⇒
明治時代から戦後まで存在した家督相続制度。長男が全てを相続し、家族に不公平感も。現代の相続制度との違いを解説!昭和22年以前の相続にも影響。

