芥川龍之介とは?〜その生涯と文学作品(?)芥川龍之介の世界:作品と文学的影響
日本近代文学を代表する芥川龍之介。鋭い人間観察と独特の文体で、エゴや社会の矛盾を描いた短編の名手。「羅生門」「蜘蛛の糸」など代表作多数。若くして自ら命を絶った彼の生涯と作品は、今もなお文学界に深い影響を与え続けている。
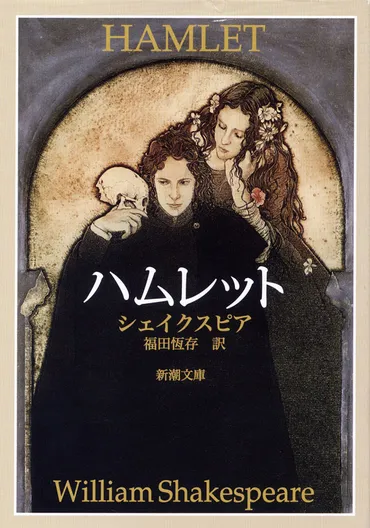
💡 芥川龍之介は、日本の近代文学を代表する作家であり、短編小説の名手として知られています。
💡 彼の作品は人間の心理描写に優れ、エゴイズムや社会問題を鋭く描き出しました。
💡 晩年は神経衰弱に苦しみましたが、彼の文学的遺産は今もなお多くの人々に影響を与え続けています。
それでは、生い立ちから作品の特徴、晩年まで、芥川龍之介の人生と文学について、詳しく見ていきましょう。
生い立ちと文学への目覚め
芥川龍之介、文豪への道!どんな生い立ち?
伯母に育てられ、古典と西洋文学に親しんだ。
芥川龍之介は、幼少期から文学に親しみ、東京帝国大学でシェイクスピアを学びました。
初期の創作活動から文才を発揮し、文壇デビューを果たしました。
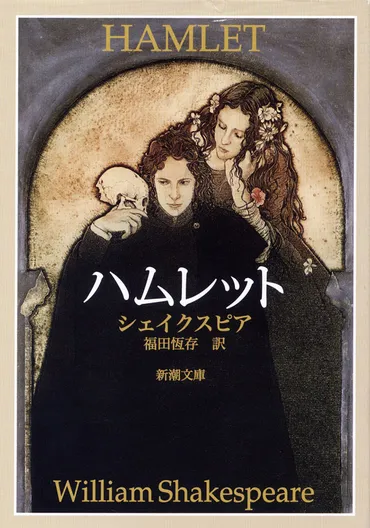
✅ シェイクスピアの悲劇『ハムレット』は、父王の亡霊から叔父による殺害を告げられた王子ハムレットが復讐を誓う物語。
✅ ハムレットは狂気を装いながらも、葛藤しつつ復讐を遂げるが、自身も命を落とす。悲恋の相手オフィーリアの存在も描かれている。
✅ 本書は福田恆存による翻訳で、新潮文庫から配信されている。
さらに読む ⇒新潮社の電子書籍出典/画像元: https://ebook.shinchosha.co.jp/book/E024781/『ハムレット』は、シェイクスピアの代表作の一つですね。
福田恆存氏による翻訳で、読みやすい形で提供されているのは素晴らしいです。
芥川龍之介は、1892年3月1日に東京で生まれました。
生後間もなく母親が精神疾患を発症し、伯母に育てられました。
幼少期には古典文学に親しみ、教育熱心な芥川家で育ちました。
東京帝国大学英文学科に進学し、シェイクスピアなどの西洋文学を学び、回覧雑誌での創作活動を経て文才を開花させました。
芥川は幼少期から古典文学に親しんでいたんですね。その経験が、後の彼の作品にどのように影響したのか興味深いです。
作家としての成功と作風の確立
芥川龍之介、文壇デビューのきっかけは?
夏目漱石に師事し「鼻」を発表。
芥川龍之介は、大学時代に文壇デビューを果たし、人間のエゴや醜さを描く作風を確立しました。
代表作「羅生門」など、初期作品が高く評価されました。

✅ 様々なカテゴリーの本棚が提示されており、宮沢賢治作品や詩集、長編文学、評論・随筆などが分類されている。
✅ 各カテゴリーには作品名と日付が掲載されており、評論・随筆の量が最も多い。
✅ 作品は様々な作家によって書かれており、幅広いジャンルにわたっている。
さらに読む ⇒明かりの本–宮沢賢治や谷崎潤一郎などおすすめ文学を全文縦書き0円で読めます。解説やあらすじも書いてます。ネタバレ注意ですが、ぜひご一読ください。出典/画像元: https://akarinohon.com/%E6%96%87%E5%AD%A6/%E8%9C%98%E8%9B%9B%E3%81%AE%E7%B3%B8-%E8%8A%A5%E5%B7%9D%E9%BE%8D%E4%B9%8B%E4%BB%8B/様々なジャンルの作品が並んでいるのですね。
芥川龍之介の作品だけでなく、幅広い作家の作品に触れられるのは良いですね。
大学では、後の文壇を担う菊池寛らと出会い、第四次「新思潮」を創刊。
夏目漱石に師事し、「鼻」を発表して高く評価され文壇デビューを果たしました。
この時期に、人間のエゴや醜さを鋭く描く作風を確立し、代表作となる「羅生門」を発表しました。
初期作品では、人間の虚栄心や倫理的葛藤を鋭く描き、独自の視点と表現力で高い評価を得ました。
彼の文学は、母の死や家庭環境の影響を受け、鋭い観察力と深い人間洞察に基づいています。
結婚後、大阪毎日新聞社と契約し専業作家として活動を開始、「蜘蛛の糸」など児童文学も手掛けました。
夏目漱石に師事していたなんて、すごいですね!「鼻」で文壇デビューというのは、まさに実力ですね。
次のページを読む ⇒
芥川龍之介、短編小説の名手。象徴主義的表現、人間心理の深淵を描く。社会と個人の葛藤、文学的技巧が光る作品群。文学界に影響を与え続ける。

