徳川家康と鉛筆:意外な一面と日本の鉛筆文化の発展とは?鉛筆と徳川家康、そして三菱鉛筆の歴史
戦国武将・徳川家康は、実は鉛筆好きだった!? 大河ドラマで注目の家康が愛した鉛筆を通して、日本の鉛筆文化の黎明期を紐解きます。海外文化への好奇心旺盛な家康から、国産鉛筆開発に情熱を燃やした眞崎仁六まで。技術革新と歴史が詰まった鉛筆の進化を辿り、日本の文化を彩る筆記具の奥深さを感じてください。
国産鉛筆への挑戦と夜明け
明治時代、鉛筆需要が急増した理由は?
近代化と教育制度の普及のため。
明治時代に入ると、国産鉛筆の製造が始まり、教育の普及とともに需要が高まりました。
国産鉛筆の開発に尽力した人々の努力について解説します。
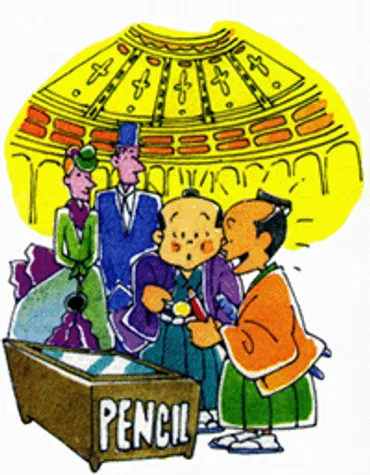
✅ 明治時代になり、教育制度が整い鉛筆の需要が高まったため、国産鉛筆の製造が始まった。
✅ オーストリアやドイツに伝習生を派遣して技術を習得させたり、国産鉛筆の製造を試み、小池卯八郎さんが国産鉛筆を初めて製作した。
✅ 眞崎仁六さんが鉛筆の製造法を研究し、水車を動力とする鉛筆工場を建設するなど、国産鉛筆の普及に貢献した。現在でも鉛筆製造で培った技術を活かし、様々な筆記具が作られている。
さらに読む ⇒鉛筆|東京鉛筆組合昭午会ボクも!ワタシも えんぴつ大好き出典/画像元: http://www.pencil.or.jp/rekishi/rekishi6/rekishi6.html明治時代に国産鉛筆の製造が始まった背景には、教育の普及があったのですね。
当時の人々の熱意が伝わってきます。
鉛筆が日本に伝来した後、明治時代に入ると、近代化と教育制度の普及に伴い、鉛筆の需要が急増しました。
それまでの筆記具の不便さを解消するため、国産鉛筆への挑戦が始まります。
明治6年(1873年)には、海外で鉛筆製造技術を学んだ伝習生が帰国し、小池卯八郎が国産鉛筆の製造を開始。
小池の鉛筆は、1877年の「第1回内国勧業博覧会」で「教育ノ器具」として出品され、国産鉛筆の可能性を示しました。
鉛筆が国産化されるまでの過程は、まさに日本の近代化そのものですね。興味深いお話です。
三菱鉛筆の誕生と革新
国産鉛筆の父、眞崎仁六は何を成し遂げた?
国産鉛筆の製造と三菱鉛筆の創設。
三菱鉛筆の創業者、眞崎仁六は、理想の鉛筆を作るために10年の歳月を費やしました。
その情熱と、三菱鉛筆の誕生秘話に迫ります。

✅ 鉛筆の歴史は16世紀の英国に始まり、日本には17世紀に伝来。明治時代に国産化を目指した眞崎仁六は、10年の歳月をかけて理想の芯と木材を追求し、国産鉛筆製造を開始した。
✅ 眞崎仁六は、黒鉛と粘土の配合や国産材料の探索に苦心し、最終的に鹿児島県産の黒鉛と栃木県産の粘土の組み合わせに辿り着いた。更に、北海道産のアララギを軸材として採用した。
✅ 眞崎鉛筆製造所(現三菱鉛筆)は、1887年に設立され、その後の技術革新により、1958年に高級鉛筆ブランド「uni」を開発し、高品質な鉛筆作りを追求し続けている。
さらに読む ⇒CBC web【CBC公式ホームページ】出典/画像元: https://hicbc.com/magazine/article/?id=news-ronsetsu-post-2395眞崎仁六氏の鉛筆にかける情熱はすごいですね。
10年もの歳月をかけて理想の鉛筆を追求したというところに感銘を受けました。
国産鉛筆の歴史において、眞崎仁六の功績は欠かせません。
彼は1878年のパリ万国博覧会で鉛筆に魅了され、国産化を決意。
理想の鉛筆芯と軸を求めて10年の歳月をかけ研究を重ねました。
その結果、鹿児島県産の黒鉛と栃木県産の粘土を組み合わせた芯を開発し、北海道産のイチイ科のアララギを軸材として採用。
1887年、眞崎は「眞崎鉛筆製造所」を設立し、これが現在の三菱鉛筆株式会社の始まりです。
眞崎仁六氏の鉛筆作りにかける情熱、そして三菱鉛筆の誕生秘話、とても興味深かったです。
日本の鉛筆文化の発展と未来
三菱鉛筆「uni」の成功の鍵は?
技術革新と、眞崎仁六の努力
日本の鉛筆文化は、眞崎仁六の努力によって発展しました。
その後の技術革新と、日本の鉛筆文化の未来について考察します。

✅ 真崎仁六は、日本初の鉛筆工業を創始した人物で、18歳で長崎留学、その後貿易会社勤務を経て、海外博覧会で鉛筆の製造を決意した。
✅ 帰国後、研究と試作を重ねて芯を完成させ、明治20年に真崎鉛筆製造所を設立。製造法研究、工場経営、販路開拓に尽力した。
✅ 三菱の商標登録や、東京・ロンドン博覧会での受賞など、その鉛筆は高い評価を受け、創造力と不屈の精神は町民の誇りとなっている。
さらに読む ⇒さがの歴史・文化お宝帳出典/画像元: https://www.saga-otakara.jp/search/detail.html?cultureId=669三菱鉛筆は、技術革新を続け、高級鉛筆「uni」を発売するなど、常に進化を続けているんですね。
日本の鉛筆文化の発展が楽しみです。
三菱鉛筆は、良質な芯を追求し、1958年には高級鉛筆「uni」を発売するなど、技術革新を続けてきました。
眞崎仁六の努力が、国産鉛筆の歴史を切り開き、日本の鉛筆文化を支えています。
現在も多くの企業が100年以上の歴史を持ち、日本の鉛筆文化を支え続けています。
筆記具の歴史は、日本の文化の歩みと共に発展しており、今後もその進化が期待されます。
三菱鉛筆の更なる発展を期待しています!
本日は、徳川家康と鉛筆、そして日本の鉛筆文化の発展についてご紹介しました。
歴史と技術革新が繋がって、今の鉛筆文化があるということが分かりました。
💡 徳川家康は鉛筆を愛用し、海外文化に触れていました。
💡 明治時代には国産鉛筆の製造が始まり、教育の普及に貢献しました。
💡 三菱鉛筆の創業者、眞崎仁六の努力が日本の鉛筆文化を支えています。


