日本被団協、ノーベル平和賞受賞!核兵器廃絶への願いは届くのか?被爆者の証言が世界を動かす!!?
広島・長崎の被爆者たちの証言と行動!日本被団協がノーベル平和賞受賞!核兵器廃絶への願いを世界へ届け、平和な未来を創造する!
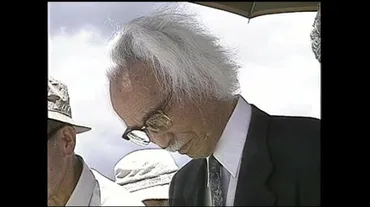
💡 日本被団協は、被爆者たちの証言を通して核兵器廃絶を訴える活動を続けてきた組織です。
💡 長年の活動が評価され、2024年にノーベル平和賞を受賞しました。
💡 しかし、核兵器の脅威は依然として存在しており、核廃絶に向けた課題も多く残されています。
それでは、日本被団協の設立から最新の活動まで、詳しく見ていきましょう。
被団協の設立と初期の活動
被爆者運動の原動力となった団体は?
日本被団協
被爆者の方々の核兵器に対する思いと、平和を希求する強い意志を感じます。
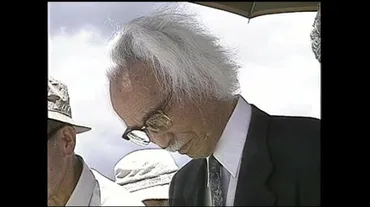
✅ 日本被団協は、1955年の第一回原水爆禁止世界大会で被爆者の声が世界に発信されたことをきっかけに翌年結成され、被爆者援護と核兵器廃絶を訴えてきました。
✅ 被爆者たちは国連軍縮会議でのスピーチや核実験に対する抗議活動など、精力的に活動を続け、核兵器の脅威と被爆による苦しみを世界に訴えてきました。
✅ 長年にわたる活動が評価され、日本被団協は2023年のノーベル平和賞を受賞しました。これは、核兵器廃絶への取り組みが国際的に認められたことを意味するだけでなく、被爆者たちの核兵器廃絶への強い意志と決意を示すものです。
さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1487104?page=2被爆者の方々の苦しみと、核兵器廃絶への願いが伝わってくるお話でした。
1956年、広島と長崎の被爆者たちは、核兵器廃絶を訴えるため、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)を設立しました。
この団体は、被爆者たちの経験と証言を世界に伝え、核兵器の非人道性を訴え続けてきました。
設立当初から、森滝市郎さんや山口仙二さんなど、多くの被爆者たちがリーダーシップを発揮し、運動を牽引してきました。
森滝市郎さんは、広島大の教授として被爆を経験し、戦後は反核運動に力を注ぎ、被団協の初代代表委員を務めました。
彼は、生涯500回近くに及んだ座り込みや、核と人類は共存できないという理念を打ち出し、被団協の礎を築きました。
山口仙二さんは、長崎で被爆し、被災協を設立、被団協の結成にも参画しました。
行動力と鋭い舌鋒で「闘士」と呼ばれ、被爆者援護法の制定を国に働きかけるなど、運動を先導しました。
彼の「ノーモア」の言葉は、被爆者運動のスローガンとして受け継がれています。
森滝市郎さんや山口仙二さんのようなリーダーがいたからこそ、日本被団協はここまで活動できたんですね!
ノーベル平和賞受賞と評価
日本被団協がノーベル平和賞を受賞した理由は?
核兵器廃絶運動への貢献
受賞の理由は、長年、被爆者の証言を通して核兵器廃絶を訴えてきた活動が評価されたとのことですね。
公開日:2024/10/15

✅ 2024年のノーベル平和賞は、被爆者の全国組織である日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)に授与されました。
✅ 日本被団協は、長年にわたり被爆者の証言を通して核兵器のない世界の実現を目指し、核廃絶運動を展開してきたことが評価されました。
✅ 特に、2016年から開始した核兵器禁止条約の署名活動や交渉会議への被爆者派遣などが条約実現に大きく貢献したことが高く評価されています。
さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02166/被爆者の証言が世界に大きな影響を与えたということがよく分かります。
2024年、日本被団協は、長年の活動が評価され、ノーベル平和賞を受賞しました。
授賞理由は、被爆者の立場から世界に核兵器廃絶を訴えてきた活動に対してです。
特に、広島と長崎の被爆者による草の根運動である日本被団協が、「核兵器のない世界実現を目指して努力し、核兵器は二度と使われてはならないのだと目撃者の証言から示したこと」が評価されました。
ノーベル委員会は、被爆者の証言が「核のタブー」と呼ばれる規範の成立に大きく貢献したと述べています。
これは、核兵器の使用が道徳的に受け入れられないという認識を世界的に高めた証言の力によるものです。
また、被爆者の個人的な経験や教育運動が、核兵器の拡散と使用に反対する動きを広げ、世界的な合意形成に独特の役割を果たしたとも述べられました。
被爆者の方々の証言が「核のタブー」と呼ばれる規範の成立に大きく貢献したというのは、とても興味深いですね。
核兵器の脅威と将来への課題
核兵器はなぜ今なお脅威なのか?
刷新・取得・戦争の脅威
核兵器の脅威は依然として存在し、核廃絶に向けた取り組みは今後も重要ですね。
公開日:2024/10/11

✅ 2024年のノーベル平和賞は、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)に授与されました。これは、被爆者の立場から世界に核兵器廃絶を訴えてきた活動を評価したものです。
✅ 授賞理由は、日本被団協が被爆者の証言を通して「核のタブー」の形成に貢献したことです。被爆者の経験と証言が、核兵器の使用は道徳的に受け入れられないという国際的な認識の形成に大きく貢献し、核兵器の拡散と使用に反対する動きを世界規模で広げました。
✅ しかし、近年は核兵器の近代化や新規取得などが進み、核兵器の使用の可能性も高まっていることから、ノーベル委員会は核兵器の脅威に対する危機感を表明しました。日本被団協は、被爆者の経験を未来世代に継承し、核兵器のない世界の実現に向けて活動を続けていくことを期待されています。
さらに読む ⇒BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio出典/画像元: https://www.bbc.com/japanese/articles/ckgnp02v5r0o核兵器の脅威は依然として大きいということがよく分かりました。
ノーベル委員会は、現状では核のタブーが圧力にさらされているという懸念も表明しました。
核保有国が核兵器を刷新していること、新たに核兵器を取得しようとする国々があること、そして戦争の脅威が続いていることから、核兵器は今なお大きな脅威であると強調されました。
日本被団協は、被爆者証言を記録し、世論に働きかけ、国際機関に代表団を送り続け、非核化の必要性を訴え続けてきました。
ノーベル委員会は、今後の非核化に向けた活動に、若い世代が被爆者の経験とメッセージを継承していくことが重要であると指摘しました。
ノーベル委員会が、若い世代が被爆者の経験とメッセージを継承していくことの重要性を指摘しているのは、重要なポイントですね。
受賞の意義と今後の展望
日本被団協のノーベル平和賞受賞は、何を示しているのでしょうか?
核廃絶への貢献
受賞は、被爆者の方々の核廃絶への願いと努力が認められた証ですね。
公開日:2024/12/10

✅ 日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。
✅ 授賞理由は、核兵器の非人道性を語り継ぎ、核廃絶の必要性を訴えてきた活動です。
✅ 代表委員の田中熙巳さんは授賞式で演説し、人類が核兵器で自滅しないよう訴えました。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASSDB3RGKSDBPTIL00QM.html日本被団協の受賞は、核廃絶に向けた取り組みの重要性を再認識させられます。
日本被団協のノーベル平和賞受賞は、被爆者たちの核廃絶への思いと、核兵器の非人道性を訴え続ける草の根運動が評価された結果です。
日本被団協は、70年近くにわたり原爆被害の甚大さを訴え続け、核軍縮運動を牽引してきた功績が認められました。
この受賞は、核軍縮への流れが停滞する現状への危機感を反映しており、核兵器のタブー化に貢献した日本被団協の活動が国際的に高く評価されたことを示しています。
授賞決定を受けて、国内外から多くの賛辞と期待の声が寄せられ、核廃絶に向けた取り組みの重要性が再認識されました。
日本被団協の活動は、核軍縮への流れが停滞する現状において、大きな意味を持つと思います。
平和への願いと行動
広島の高校生が作った折り鶴は何を象徴している?
平和への願い
広島の高校生が制作した折り鶴は、平和への願いを世界に伝える象徴ですね。

✅ 広島の高校生が制作した銅製の折り鶴が、12月10日にノルウェーの首都オスロで開催される日本原水爆被害者団体協議会(被団協)へのノーベル平和賞授賞式に際し、現地要人に贈られる。
✅ 折り鶴は被団協の箕牧智之事務局長がオスロに持参する。
✅ 折り鶴は、広島の高校生らが平和への願いを込めて制作したもので、被爆の記憶と平和への願いを世界に伝える役割を担う。
さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL 静岡県のニュース出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1610422折り鶴を通して、平和への願いが世界に届けられることを願っています。
一方で、世界には依然として厳しい現実があり、核兵器の脅威は依然として存在しています。
日本も米国の核の傘に頼る現状など、核軍縮に向けた課題は多く残されています。
広島市立広島みらい創生高校の生徒2名が、日本被団協のノーベル平和賞授賞式でノーベル委員会などに贈呈される銅製の折り鶴を制作しました。
この折り鶴は、戦争の恐ろしさや平和の大切さを伝えるために、日本被団協の箕牧智之代表委員が制作を依頼したものです。
生徒たちは、かつてローマ教皇にも銅製の折り鶴を贈った経験を持つ沢田和則先生から指導を受け、厚さ0.1mmの銅板を丁寧に折り鶴に仕上げました。
制作には1か月かかり、平和への願いが込められています。
生徒たちは、今回の制作を通して平和への思いを新たにし、「歴史を風化させない」「戦争が少しでも良い方向に進んでほしい」と語りました。
箕牧代表委員は、この折り鶴が平和のシンボルであり、核兵器の廃絶と平和への願いを世界に訴えかけるものと期待しています。
戦争の恐ろしさや平和の大切さを伝える折り鶴、素晴らしいですね。
日本被団協の活動は、核兵器廃絶への取り組みの重要性を改めて認識させてくれます。
💡 日本被団協は、被爆者の証言を通して世界に核兵器の非人道性を訴え続けてきました。
💡 長年の活動が評価され、2024年にノーベル平和賞を受賞しました。
💡 核兵器の脅威は依然として存在しますが、被爆者たちの願いと行動は、世界を変える力を持っていることを示しています。


