太平洋戦争の真実:見過ごされた分析と食糧問題?開戦に至るまでの日本の選択と食糧問題
1941年、日本は゛日本必敗゛の開戦シミュレーションを無視し、太平洋戦争へ。食糧危機を隠蔽し、資源確保のため南部仏印進駐を強行。本書は、最新の数値分析で、ミッドウェー海戦や零戦の性能、海上輸送の脆弱性など、従来の歴史観を覆す事実を提示。食糧問題の重要性、指導層の判断ミスがもたらした結果を詳細に分析し、過去の教訓から未来への警鐘を鳴らす。
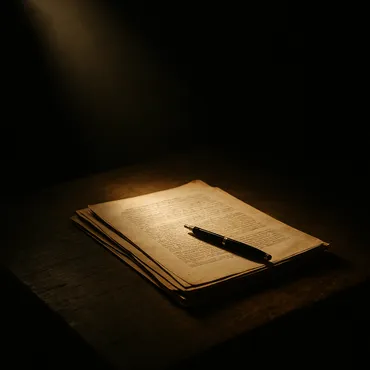
💡 総力戦研究所の分析が、開戦直前に「日本必敗」という結論を出していた。
💡 食糧不足が深刻化し、南部仏印進駐は食糧確保という目的があった。
💡 定量分析により、ミッドウェー海戦などの戦闘を多角的に評価する研究が進んでいる。
本日は、太平洋戦争の知られざる側面、特に開戦に至るまでの政府内の動きと食糧問題に焦点を当てて解説していきます。
開戦への道:見過ごされた分析と食糧問題
日米開戦を左右した、日本政府のシミュレーション結果とは?
「日本必敗」長期消耗戦での劣勢が予測された。
太平洋戦争開戦前、日本政府は様々な分析を行っていました。
その中でも、総力戦研究所の活動は、開戦の是非を左右する重要なものでした。
公開日:2025/08/16
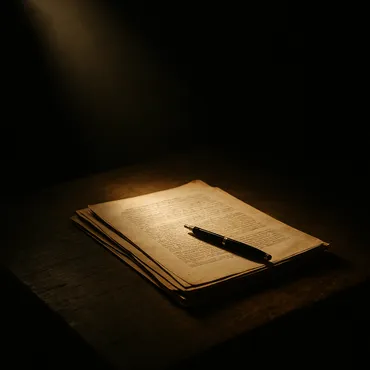
✅ NHKスペシャル「シミュレーション昭和16年夏の敗戦 前編」は、首相直轄の極秘機関「総力戦研究所」の活動を、ドラマとドキュメントで描いた番組であり、開戦の是非を議論する若者たちの姿や、白井正辰陸軍大尉をモデルにした人物の活躍が描かれた。
✅ 総力戦研究所は、陸軍や海軍だけでなく、各官庁や民間企業からも選ばれたエリートが集まり、経済力や外交関係、国民生活を含めた国家総動員をシミュレーションし、開戦を避けるためにリスクを分析することを目的としていた。
✅ 研究所の設立と運営を主導した飯村穣陸軍中将は、自由に意見を交わせる環境を整え、机上演習を通して「日米戦うべからず」と警告を発していた。孫の飯村豊さんが保管する資料からは、当時の研究員たちの真剣な姿勢が伝わる。
さらに読む ⇒気になるNHK出典/画像元: https://nhk.shigeyuki.net/?p=9527総力戦研究所のシミュレーション結果を無視したことは、非常に残念です。
もし耳を傾けていたら、日本の運命は変わっていたかもしれません。
1941年、日米開戦の3ヶ月前、日本政府は「総力戦研究所」を設立し、陸海軍、官僚、民間エリートを集めて開戦シミュレーションを実施しました。
この「模擬内閣」は、厳しい国力分析に基づき「日本必敗」という結論を導き出し、長期消耗戦における日本の劣勢を詳細に分析しました。
しかし、東条英機陸相(後の首相)はこの提言を無視し、開戦への道を進みました。
研究所の所長であった飯村元陸軍中将は、このシミュレーションの目的を、軍内部での対米開戦への楽観論を払拭し、長期戦の困難さを理解させるためであったと述べています。
この無視された分析は、日本の将来を決定的に左右することになります。
さらに、1941年7月の南部仏印進駐は、資源確保、特に石油が主な理由とされていますが、実は食糧資源、とりわけ仏印(ベトナム)とタイからの米の確保が重要な要素でした。
当時の日本は900万石の米が不足しており、食糧危機は「軍事上経済上政治上ノ見地ヨリ」南部仏印への進駐の「絶対必要」性を裏付けるものとなりました。
東條英機陸相はこれを「大決定」と表現し、食糧確保が戦争遂行における重要な要素であったことを示唆しています。
とても興味深い内容でした。開戦前に、日本がそこまで詳細な分析をしていたとは驚きです。東条英機の判断が、その後の日本の命運を大きく左右したと思うと、歴史の重みを感じます。
定量分析が示す太平洋戦争の実相
大東亜戦争の戦闘分析、何が新しくて重要?
定量的なデータに基づく比較分析が重要。
近年、太平洋戦争を多角的に分析する研究が増えてきました。
定量分析によって、新たな視点から戦争の実相に迫ろうとしています。

✅ ミッドウェー海戦では日本海軍は主力空母4隻を失い、優秀な搭乗員も多く失った。
✅ 敗戦後、山本五十六は責任を問うことはなかったものの、南雲の生き残りと山口多聞の戦死に対して複雑な感情を抱いていたと考えられる。
✅ ミッドウェー海戦の敗北は日本海軍に大きな衝撃を与え、その後の作戦に影響を及ぼし、ガダルカナルでの反攻を招く原因となった。
さらに読む ⇒BEST TiMES(ベストタイムズ)|日常をちょっと豊かにするメディア出典/画像元: https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/4907/ミッドウェー海戦や零戦の性能分析など、従来の認識を覆すような分析結果には驚かされます。
データに基づいて評価することで、より客観的な視点が得られますね。
近年、大東亜戦争をテーマにした数値分析が注目を集めています。
従来の戦争研究における定性的な分析に加え、ミッドウェー海戦やソロモン海戦など、太平洋戦争における主要な戦闘を、航空索敵能力、目標到達能力、防空能力、攻撃能力、ダメージコントロール能力といった観点から定量的に比較分析することが重要とされています。
例えば、ミッドウェー海戦における日本軍の索敵機の少なさや、日米の爆撃命中率の比較など、従来の認識を覆す分析結果が示されています。
また、零戦とワイルドキャットの性能比較や、戦艦大和のアウトレンジ戦法の有効性、日本海軍戦艦の実力についても、具体的なデータに基づいて評価されています。
私も、数値で分析することで、今まで見えなかった部分が見えてくるのは面白いと思いました。零戦とワイルドキャットの性能比較とか、もっと詳しく知りたいです!
次のページを読む ⇒
太平洋戦争下の日本の食糧問題を徹底分析。失敗の本質を浮き彫りにし、指導層の過ちと教訓を明らかに。現代社会への警鐘を鳴らす、歴史的考察。

