平安時代の化粧ってどんなもの?貴族が実践した美の秘訣とは?平安時代の化粧:白粉、紅、眉、お歯黒が彩る美の世界
平安時代、日本独自の美意識が花開いた。白粉で白く、紅で彩り、引眉で整える洗練された化粧は、貴族女性のステータス。単なる装飾ではなく、社会的な価値観を表現。美白と眉化粧が重要視され、男性にも広がり、身分を示す象徴に。暗い室内で映える化粧は、現代の美意識にも通じる。日本独自の化粧文化の基礎を築いた雅な世界。
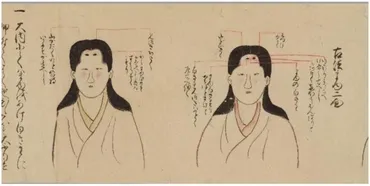
💡 平安時代の化粧は、白粉による白い肌、紅による赤色の表現、引眉による特徴的な眉が特徴。
💡 化粧道具として、白粉箱や紅皿が使われ、現代とは異なる素材や技術で美を追求していた。
💡 洗顔には澡豆や皂莢などを使用し、保湿には獣脂や植物の汁を使用し、スキンケアもおこなっていた。
今回は、平安時代の化粧に焦点を当て、その特徴や変遷、当時の美意識について掘り下げていきます。
平安美人の魅力と、その裏にある工夫を紐解きましょう。
平安時代の美への幕開け:化粧と美意識
平安時代の美の象徴とは?化粧は何のため?
白粉、紅、引眉。身だしなみであり、価値観。
平安時代は、日本独自の美意識が花開いた時代。
貴族の女性たちは、白粉、紅、引眉を施し、美しさを追求しました。
今回は、その化粧文化の幕開けについて見ていきましょう。
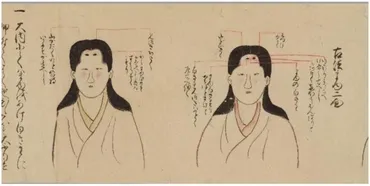
✅ 平安時代の化粧は、眉を剃り白粉で塗りつぶした後に高い位置に太い眉を描くのが特徴で、『源氏物語』にもその様子が描写されている。
✅ それまでの化粧は唐風で、ポイントメイクや弓なりの眉など華やかだったが、平安時代には白粉、紅、おちょぼ口が主流となった。
✅ 眉を抜く風習の理由は明確ではないものの、時代や流行によって化粧も変化するということが言える。
さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/228465平安時代の化粧は、現代とは異なり、顔全体を白く塗り、眉を剃り落として高い位置に描くなど、独特ですね。
当時の美意識が、化粧を通して表現されていたことが分かります。
平安時代は、日本独自の美意識が花開いた時代であり、特に宮廷文化の中で洗練された化粧が発展しました。
貴族の女性たちは、顔を白くする白粉、頬や唇を彩る紅、特徴的な眉の描き方である引眉を施し、美しさを追求しました。
これは単なる装飾ではなく、当時の社会的な価値観を反映したものであり、寝起きの素顔を人に見せることを恥ずかしいと感じるほど、化粧は重要な身だしなみの一部でした。
興味深いですね。寝起きの素顔を見せるのを恥ずかしいと感じるほど、化粧が重要だったとは。現代のメイクとはまた違った、当時の美への価値観が垣間見えます。
平安貴族の顔づくり:化粧方法と化粧道具
平安美人の鍵は何? 色、眉、そして健康への影響とは?
白・赤・黒の化粧、引眉、そして鉛白粉の健康問題。
平安時代の化粧は、唐風から変化し、独自の進化を遂げました。
白粉、紅、眉化粧、お歯黒を用いた宮廷メイクは、高い身分を示す象徴となりました。
その方法と道具に迫ります。

✅ 平安時代の化粧は、唐風の華やかなメイクから変化し、白粉、紅、眉化粧、お歯黒を用いた独自の宮廷メイクが発展した。
✅ 眉化粧とお歯黒は、平安貴族の間で一般化し、特に眉化粧は感情を抑えた美しさを表現するために行われた。
✅ 平安時代末期には公家の男性も化粧をするようになり、化粧は高い身分を示す象徴となった。この白・赤・黒の化粧は江戸時代まで続き、日本独自の化粧文化を形成した。
さらに読む ⇒ポーラ文化研究所出典/画像元: https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/culture/cosmehistory/009.html白粉に鉛が使われていたとは驚きです。
見た目を美しくする一方で、健康への影響もあったんですね。
また、画一的な美を目指していたという点も、興味深いです。
平安時代の洗練された美しさを表現するために、白、赤、黒の3色が中心となって化粧が施されました。
顔を白く見せるための白粉には鉛が使われましたが、健康被害も問題となりました。
紅は頬や唇を彩り、爪にも塗られました。
特徴的な引眉は、眉を抜き、眉墨で本来の位置より上に描くことで、顔全体のバランスを整えました。
化粧道具としては、白粉箱や紅皿などが使用され、これらの化粧法は、暗い室内環境下で顔を際立たせるために考案されたと考えられています。
画一的な美を追求し、皆が似たような「画一的な美女」を目指す傾向がありました。
鉛入り白粉の話は衝撃的でした!でも、それだけ美を追求していたんですね。現代とは違う美の価値観を感じます。
次のページを読む ⇒
平安時代の美意識を探求。洗顔、保湿から、白粉、引眉まで。貴族たちの化粧は、身分と美を象徴し、日本独自の化粧文化の礎となった。

