長篠の戦い(1575)とは?信長と勝頼、激突!鉄砲隊と武田騎馬隊の戦い?織田信長VS武田勝頼!長篠の戦いの真実
戦国時代最大の激戦、長篠の戦い!天下を狙う織田信長vs武田信玄の遺志を継ぐ勝頼。鉄砲三段撃ちの衝撃、籠城戦、奇襲作戦…最新兵器と戦術が激突!信長の策略、家臣団の確執、そして運命の結末とは?歴史を変えた戦いの真実を、今、暴く!
設楽原の激戦と酒井忠次の活躍
設楽原の戦い、勝敗を分けたのは?
鉄砲三段撃ちと地形を活かした戦術。
織田・徳川連合軍と武田軍が激突した設楽原の戦いについて、詳細に見ていきましょう。
そこには、信長の巧みな戦略がありました。
公開日:2018/08/30

✅ 織田・徳川連合軍と武田勝頼率いる武田軍が長篠城を巡って対峙し、武田軍の攻撃に耐えかねた長篠城の兵は援軍を要請する。
✅ 援軍を要請する為に、鳥居強右衛門が岡崎城へ向かい、帰路で武田軍に捕らえられるも長篠城の兵へ激励の言葉を送った後、処刑される。
✅ 織田信長は鳶ヶ巣山砦を奇襲し、鉄砲隊を主体とした戦術と馬防柵を駆使して、武田騎馬隊を破り、武田軍を壊滅させた。
さらに読む ⇒戦国バトルヒストリー出典/画像元: https://www.sengoku-battle-history.net/nagashinotatakai/鉄砲隊と馬防柵を組み合わせた信長の戦術は、当時の戦い方を変えたといえるでしょう。
画期的な作戦ですね。
織田・徳川連合軍は、馬防柵を構築し、武田軍を挑発。
酒井忠次は夜間に険しい山岳地帯を突破し、鳶ノ巣山砦を攻略。
これらの作戦により、武田軍は退路を断たれることになった。
1575年6月29日、両軍は設楽原で激突。
織田信長の鉄砲三段撃ちが武田騎馬隊を壊滅させたというイメージが強いが、実際には、泥田や連吾川といった悪条件の中、8時間にも及ぶ激戦が繰り広げられた。
鉄砲三段撃ちのイメージが強いですが、8時間もの激戦だったという事実は、もっと知られるべきですね。
武田軍の敗北と、その要因
武田軍大敗の理由は?何が勝頼を苦しめた?
内政混乱と信長との同盟関係、そして革新的な戦術。
武田軍の敗北の原因を多角的に分析し、長篠の戦いが日本の戦史に与えた影響について考察します。
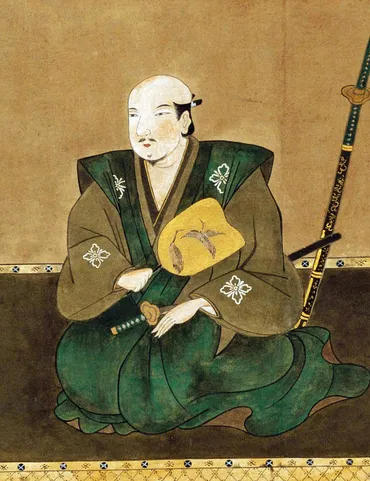
✅ 長篠の戦いは、織田信長・徳川家康連合軍と武田勝頼が三河の長篠(愛知)で戦ったもので、日本で初めて鉄砲が大規模に使用された戦いです。
✅ この戦いの原因は、武田勝頼が徳川家康の領地であった長篠城を攻略しようとしたことにあり、連戦連勝の勢いと父信玄の遺志を継ぐという勝頼の野望が背景にありました。
✅ 織田・徳川連合軍は、設楽原に柵などを築いて武田軍を待ち受け、鉄砲隊を有効活用して勝利を収めました。一方、武田軍は重臣の意見を退けて設楽原での戦闘を選んだことが敗因の一つとなりました。
さらに読む ⇒日本史事典.com|受験生のための日本史ポータルサイト出典/画像元: https://nihonsi-jiten.com/nagashinono-tatakai/武田家の名将たちが討ち死にしたのは、非常に痛手だったでしょう。
勝頼の内政的な問題も敗因に繋がったのですね。
激戦の末、山県昌景、馬場信春、内藤昌豊、土屋昌次、真田信綱ら武田の名将が討ち死にし、穴山信君ら一族衆の撤退もあって、武田軍は大敗を喫した。
この敗北は、単に信長の革新的な戦術だけではなく、武田勝頼の内政的混乱、そして信長との同盟関係の複雑さが強く影響した結果であった。
この戦いは、織田信長が鉄砲を本格的に導入し、その後の戦闘形態に大きな影響を与えたことでも知られている。
信長の鉄砲隊導入が、その後の戦闘形態に影響を与えたというのは、非常に興味深いですね。
武田家の滅亡
武田家滅亡の鍵は?勝頼を追い詰めた要因とは?
裏切り、同盟破綻、そして信長の圧力。
長篠の戦いでの敗北後、武田家が滅亡するまでの経緯を追います。
武田勝頼の最期についても触れていきます。

✅ 武田勝頼は武田信玄の四男として生まれ、父の死後、家督を継承。織田信長に対抗するも、長篠の戦いでの大敗北により武田家は衰退の一途をたどった。
✅ 長篠の戦いでは、織田・徳川連合軍の鉄砲隊に対し、武田軍は壊滅的な打撃を受け、多くの重臣を失った。勝頼は敗戦後も再建を図るが、家臣の裏切りが相次いだ。
✅ 織田信長による甲州征伐により、武田家は滅亡。勝頼は家臣の裏切りにあい、妻や嫡子と共に自害した。武田家は信玄の代から続いた勢力を失った。
さらに読む ⇒戦国サプリメント 戦国未満出典/画像元: https://sengokumiman.com/takedakatuyori.html家臣の裏切りは、勝頼にとって大きな痛手だったでしょう。
武田家の滅亡は、時代の流れを感じさせます。
長篠の戦いでの敗北後、武田勝頼は一定の勢力を保っていたものの、上杉氏との同盟破綻、信長との和睦交渉の失敗、家臣の裏切りなど、内外からの圧力が重なり、滅亡へと向かうこととなる。
天正10年(1582年)、信長の出陣命令からわずか2ヶ月足らずで、武田氏は滅亡。
勝頼は家臣である小山田信茂に裏切られ、嫡男とともに自害。
武田家の歴史は、ここに幕を閉じた。
武田家滅亡は悲しいですが、歴史の流れを感じますね。もっと武田家の栄枯盛衰を知りたいです。
長篠の戦いは、信長の革新的な戦略と武田家の衰退を描いた重要な戦いです。
鉄砲隊の導入は、その後の日本の戦国時代に大きな影響を与えました。
💡 長篠の戦いは、織田信長と武田勝頼が激突した戦いで、信長の鉄砲隊と武田騎馬隊の戦いが特徴。
💡 鳥居強右衛門の活躍は、長篠城を守るための重要なエピソードとして語り継がれている。
💡 武田軍の敗北は、信長の革新的な戦術と、武田勝頼の内政的な問題が複合的に影響した結果です。


