芥川龍之介とは?生い立ちから作品、死まで徹底解説!芥川龍之介作品の世界とその生涯
『羅生門』『鼻』…教科書でお馴染みの芥川龍之介。暗い影を落とす幼少期の経験、時代への鋭い洞察力、そして繊細な心理描写が織りなす珠玉の短編小説たち。自己の苦悩、人間のエゴイズム、死への葛藤…芥川文学は、今もなお読者の心を掴んで離さない。生誕135年、没後100年を前に、その多様な魅力を再発見!
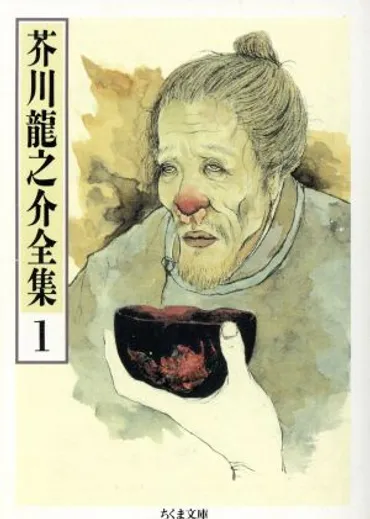
💡 芥川龍之介の生い立ちから晩年までの生涯を解説、作品が生まれた背景を理解。
💡 代表作『羅生門』『鼻』『蜘蛛の糸』などを紹介、作品の特徴や魅力に迫る。
💡 教科書掲載作品や教育現場での芥川作品の役割、その魅力を考察します。
今回は芥川龍之介の生涯と作品について、深く掘り下げていきます。
彼の生い立ち、作品の特徴、そして晩年について、詳しく見ていきましょう。
生い立ちと文壇デビュー
芥川龍之介、文壇デビュー作は?代表作も教えて!
『羅生門』でデビュー。『羅生門』『鼻』など。
芥川龍之介は1892年、東京に生まれました。
幼少期の経験が、彼の作品に暗い影を落とすことになります。
文才に恵まれ、大学で文学を学び、夏目漱石の評価を得て文壇デビューを果たしました。
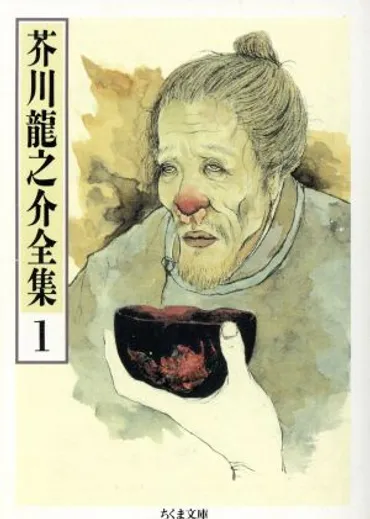
✅ 芥川龍之介の短編作品を収録した文庫本で、「羅生門」「鼻」「芋粥」など25編が収録されています。
✅ 改訂版で1986年9月1日に発売され、文庫本として販売されています。
✅ 店舗受取サービスに対応しており、店頭での在庫確認は可能ですが、オンラインストアと店頭価格は異なる場合があります。
さらに読む ⇒トップ | ブックオフ公式オンラインストア出典/画像元: https://shopping.bookoff.co.jp/used/0012016426芥川龍之介の生い立ちが作品に影響を与えていることがよくわかりますね。
『羅生門』のような作品が、どのように生まれたのか、興味深いです。
芥川龍之介は、1892年東京に生まれ、幼少期に実母の精神疾患と幼い頃の環境がその後の作品に暗い影を落とすことになります。
文才に恵まれた彼は東京帝国大学で文学を学び、1915年に『羅生門』を発表、夏目漱石の評価を得て文壇デビューを果たします。
代表作には、荒廃した平安京を舞台に人間のエゴイズムを描く『羅生門』、鼻の長さを気にする僧の心理を描いた『鼻』、自己中心的な人間の末路を描く『蜘蛛の糸』、人間として大切なものを考えさせる『杜子春』など、多様なテーマの短編小説があります。
特に『羅生門』と『鼻』は、その読みやすさから入門者にもおすすめされています。
芥川龍之介の生い立ちと作品への影響、興味深いですね。彼の作品を読み解く上で、重要なポイントになりそうです。
作品の特徴と文芸観
芥川文学、その魅力は?冷徹な視線?それとも、時代への誠実さ?
人間の内面を冷徹に描き、時代を独自の視点で構築。
芥川龍之介の作品は、人間の内面を鋭く描き出すことで知られています。
古典を題材にしながら、現代的なテーマを表現することを得意としていました。
簡潔な文体も彼の作品の特徴です。
公開日:2021/12/08
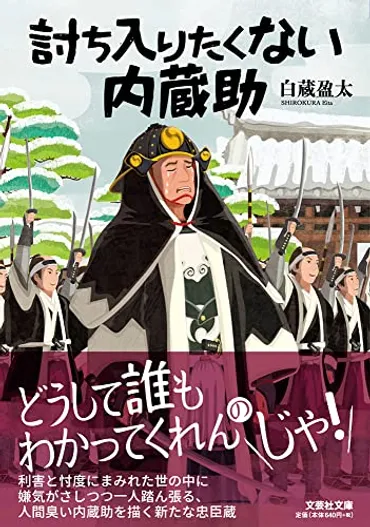
✅ 白蔵盈太氏の小説『討ち入りたくない内蔵助』は、忠臣蔵を題材とし、従来の忠義一辺倒なイメージとは異なる、等身大で人間味あふれる大石内蔵助を描いている。
✅ 物語は、松の廊下事件によって人生が暗転した大石内蔵助が、藩士たちの暴走を抑え、お家再興を目指して奔走する姿を描き、その過程で本音を吐露する内蔵助の姿が魅力的に描かれている。
✅ 下級藩士による籠城派と穏健開城派の間で揺れ動く中、内蔵助が選ぶ道が描かれ、事件を時系列で追うことで、忠臣蔵事件への理解を深めることができる作品である。
さらに読む ⇒時代小説SHOW出典/画像元: https://www.jidai-show.net/2021/12/08/b-uchiiri-takunai-kuranosuke/芥川龍之介の作品は、人間の内面を深くえぐり出すような魅力がありますね。
「人生を銀のピンセットで弄んでいる」という評も、彼の作風をよく表しています。
芥川は古典を題材に、現代的な自我の苦悩を表現することを得意とし、『或日の大石内蔵助』では忠臣蔵を題材に大石内蔵助の孤独感を描くなど、幅広い作品を発表しました。
その作品は簡潔な文体で描かれ、人間の内面を冷徹な視点で描き出すと評されています。
その作風は菊池寛をして「人生を銀のピンセットで弄んでいるような」と評されるほどでした。
一方で、彼の作品は時代状況への誠実さも特徴としており、社会主義思想に関心を示したものの、実践的な行動には繋がらないなど、時代の空気を敏感に感じ取りながらも、独自の視点で作品を構築していきました。
中村真一郎は、芥川文学の特質を「唯美的な趣味」と指摘しています。
芥川龍之介の作品は、人間の内面を鋭く描いているという点が興味深いです。社会情勢への誠実さも持ち合わせていたという点も、作品を読み解く上で重要ですね。
次のページを読む ⇒
芥川龍之介、没後100年。教科書でお馴染みの作家の多様な顔を知る。葛藤と死、家族への想い。作品は今も輝き、新たな魅力を発信し続ける。

