旧制高等学校の学生たち、学徒出陣とは? 揺れ動く青春と時代の影を追うドキュメント?学徒出陣、揺れる学生たちの青春と思想弾圧
1919年創立の旧制松本高等学校。自由な言論が育まれた校友会雑誌は、時代と共に変化する学生たちの葛藤を記録した。思想弾圧、学徒出陣…若者たちは国家指導者を目指すも、戦争の波に翻弄される。戦後80年企画展では、学問の自由を奪われ、過酷な運命を辿った学生たちの姿を展示。戦争の悲劇を風化させず、未来へ語り継ぐ。
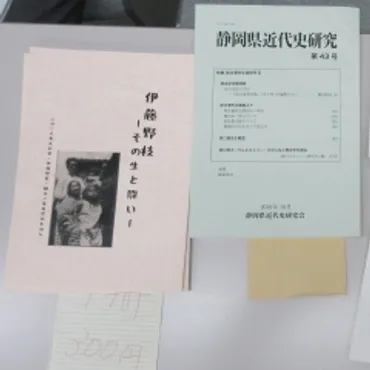
💡 旧制松本高等学校の校友会雑誌を通して、戦前の言論統制と学生たちの揺れ動く心情を読み解きます。
💡 旧制静高の学徒出陣に関する記事から、戦争という時代に翻弄された学生たちの実態を明らかにします。
💡 2025年に開催される企画展を通して、戦争の悲劇を後世に伝えるための取り組みを紹介します。
それでは、近代史研究の会報や日記、校友会雑誌などを紐解きながら、激動の時代を駆け抜けた学生たちの姿を追っていきましょう。
学問の灯火と時代の影
旧制松本高校の校友会雑誌は何を育んだ?
言論の自由と学生たちの表現の場。
1978年に創刊された会報は、静岡県の近代史研究に関する情報を発信し、自由民権運動から女性史まで多岐にわたるテーマを扱ってきました。
公開日:2025/08/01
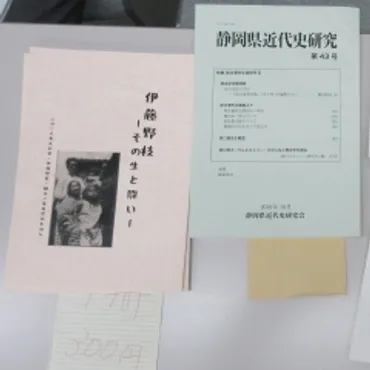
✅ 会報は1978年10月に創刊され、毎月欠かさず発行されており、2020年5月に500号を迎えました。
✅ 会報では、創刊号から20号まで、記事、新刊紹介、研究案内、例会報告、訃報など、様々な情報が掲載されました。
✅ 記事の内容は、静岡県の近代史研究に関するものが多く、自由民権運動、労働運動、社会運動、女性史など多岐にわたります。
さらに読む ⇒静岡県近代史研究会出典/画像元: https://shizuokakenkindaishi.wordpress.com/bulletin/様々な情報が掲載されており、当時の学生たちの生活や思想を知る貴重な資料となっていると感じました。
多岐にわたるテーマも興味深いです。
時は1919年、旧制松本高等学校は創立されました。
校友会雑誌は1920年から1947年まで発行され、在校生や教職員が活動報告や論文、創作物を掲載し言論の自由を育んでいました。
しかし、時代は容赦なく変化し、1930年代に入ると、治安維持法や日中戦争の勃発により、学生たちの生活は徐々に暗い影を落とし始めます。
信州大学副学長の渡邉匡一教授は、旧制松本高等学校の学生の日記を題材に講演を行い、学生たちの揺れ動く心情や、時代に翻弄されながらも国家指導者を目指す若者たちの葛藤を浮き彫りにしました。
旧制松本高等学校の学生の日記を題材にした講演は、学生たちの内面を深く掘り下げていて、非常に興味深いですね。
思想弾圧と戦争の足音
松高思想事件は学問の自由をどう変えた?
学校自治を失い、言論の自由を奪った。
香港の旧暦と新暦が混在する祝日事情は、一国両制を象徴しています。
特に、国慶節が中国人観光客増加を招いている点は興味深いですね。
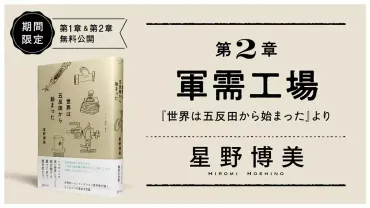
✅ 香港の暦は、旧暦の「二十四節気」を重視し、新暦と旧暦の祝日が混在している。英国統治時代の名残と中国本土の影響が共存し、一国両制を象徴している。
✅ イースターや労働節、香港特別行政区成立記念日、国慶節など、様々な祝日が設けられている。特に国慶節は中国からの観光客増加を招き、香港市民に中国化への違和感を抱かせる結果となっている。
✅ 著者の親友家族は、香港の大型連休であるイースターを利用して日本を訪れる。旧正月は中国からの観光客が多く、彼らにとって都合が悪いため、イースターにシフトした。
さらに読む ⇒ webゲンロン出典/画像元: https://webgenron.com/articles/gotanda_02香港の祝日の多様性と、中国本土の影響について、歴史的背景を理解する上で非常に参考になる情報が盛り込まれていますね。
時代は緊迫の度を増し、旧制松本高等学校にも思想弾圧の波が押し寄せます。
松高思想事件が発生し、学校の自治は失われ、校友会も解散に追い込まれます。
学内には報国団が組織され、学生たちは国家総動員法、そして徴兵制度の変化に直面します。
1920年代から1947年までの校友会雑誌の分析を通して、長野県立長野図書館長の森いづみ氏は、戦前の言論の自由が、プロパガンダへと傾倒していく様子を詳細に明らかにしました。
太平洋戦争開戦直前には、言論の自由は制限され、学生たちは学問の自由を奪われていきます。
言論統制や校友会の解散など、学生たちの置かれた状況が詳しく描写されていて、胸が締め付けられる思いです。
次のページを読む ⇒
学徒出陣、戦地からの手紙…戦後80年企画展で戦争の悲劇を伝える。自由を奪われた学生たちの記録を風化させず、未来へ。

