日本のインフレとデフレの歴史:20世紀から現代まで、ハイパーインフレのリスクは?日本経済のインフレとデフレ:歴史的背景と現代の課題
激動の日本インフレ史!1901年から現代まで、企業物価指数が映し出す波乱の物語。戦後の70倍インフレ、デフレ時代、そして現代の物価上昇。ハイパーインフレのリスクと対策を、過去の事例から学び、資産を守る術を伝授!円安メリット・デメリットも解説。あなたの資産を守るための、経済サバイバル術を今、手に入れよう!

💡 日本経済におけるインフレとデフレの歴史を、20世紀から現代までの出来事を追って解説します。
💡 ハイパーインフレの定義と、日本におけるリスクについて、過去の事例を交えて分かりやすく説明します。
💡 インフレやハイパーインフレに対する具体的な対策と、資産防衛の方法について解説します。
今回は、20世紀から現代にかけての日本のインフレとデフレの歴史を振り返り、その背景にある要因や現代におけるリスクについて、詳しく解説していきます。
激動の20世紀:インフレと日本の歩み
日本のインフレ史、第一次大戦と世界恐慌はどう影響した?
好景気はインフレ、恐慌はデフレと財政政策。
20世紀の日本は、激動の時代を経験しました。
インフレとデフレが交互に起こり、経済は大きく揺れ動きました。
今回は、この激動の20世紀におけるインフレと日本の歩みを振り返ります。
公開日:2012/10/25

✅ 日本経済は未曾有の危機にあり、政府は財政支出増加を決めたが、雇用問題の深刻化は避けられないと指摘されている。
✅ リフレ政策こそが重要であり、貨幣ストックを大幅に増加させる必要があると主張されている。
✅ 日銀の量的緩和はリフレ政策ではなく、日銀はゼロインフレを目標としていると分析されている。
さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/10439?display=b第一次世界大戦中の好景気による物価上昇、そしてデフレへの転換と、その後の世界恐慌時の高橋是清による財政政策など、歴史的な流れを改めて整理することで、現代の経済を読み解くヒントが得られます。
1901年から現代までの日本のインフレの歴史は、企業物価指数の推移を通じて見ることができます。
第一次世界大戦中の好景気は物価上昇をもたらしましたが、その後デフレに転じました。
1929年の世界恐慌下では、高橋是清による財政政策が経済回復を促しました。
第一次世界大戦中のインフレとデフレの変動、そして世界恐慌時の財政政策など、興味深いですね。当時の経済状況を理解することは、現代の経済を考える上でも重要だと感じました。
戦後の混乱とハイパーインフレの影
戦後日本のインフレ、最高何%?国民生活はどうなった?
125%上昇。国民生活は厳しく、復興は困難。
第二次世界大戦後の日本は、未曾有の混乱を経験しました。
GHQによる改革、ハイパーインフレ対策、そしてその後のデフレと、日本経済は激しい変化を遂げました。
この章では、戦後の混乱とハイパーインフレの影に迫ります。
公開日:2022/08/01
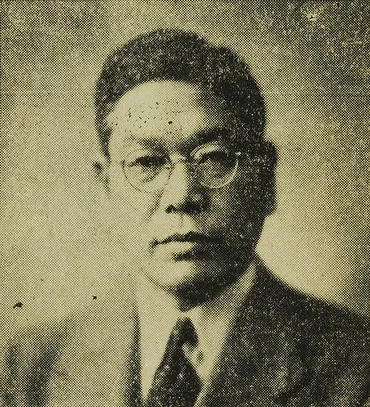
✅ 第二次世界大戦の敗戦後、日本経済は混乱し、GHQによる財閥解体、経済民主化政策、ハイパーインフレ対策としてのドッジ・ラインの実施などが行われた。
✅ インフレ抑制のため、緊縮財政、固定相場設定、農地改革が実施されたが、デフレ(ドッジ不況)が発生。その後、労働運動の弾圧や朝鮮戦争勃発に伴う朝鮮特需が発生した。
✅ 日本経済は、GHQの思惑を超え、財閥解体後の経営陣若返りや官僚機構の存続、そして朝鮮特需を機に「官民一体」となり、高度成長を遂げることになった。
さらに読む ⇒小説を 勝手にくくって 20選!出典/画像元: https://nmukkun.hatenablog.com/entry/2022/08/02/070200戦後の日本経済は、様々な政策と激しいインフレ・デフレに見舞われ、その経験は、現代の経済政策を考える上でも非常に示唆に富んでいます。
GHQによる改革やドッジ・ラインなど、詳細な解説に学ぶ点が多いですね。
第二次世界大戦後の日本は、供給能力の著しい不足と復興需要により、1945年から1949年にかけて激しいインフレに見舞われました。
物価は70倍に上昇し(1947年には年率125%を記録)、深刻な状況でした。
政府は金融引き締めを試みましたが、復興を妨げる可能性もありました。
1949年のドッジラインによる緊縮財政はインフレを抑制しましたが、デフレと安定恐慌を招き、多くの企業倒産と失業者を生み出しました。
経済学者フィリップ・ケーガンの定義では、月間50%以上のインフレ率がハイパーインフレとされますが、戦後の日本はそこまでの水準には達していませんでした。
しかし、物価上昇は国民生活に大きな影響を与え、厳しい時代となりました。
戦争の混乱とインフレ、そしてドッジラインによるデフレと、まさに激動の時代だったんですね。教科書で学ぶだけでは分からない、当時の人々の苦労が伝わってきます。
次のページを読む ⇒
高度経済成長から平成デフレ、そして再びインフレへ。ハイパーインフレのリスクと、それに備えるための資産運用術を解説。経済変動に強い資産とは?

